I/O通信を簡単に無線化【Radioline】 ~シリアル通信 具体例~

Radiolineでシリアル通信って、どんな感じなんだろう?



こんな感じに使えますよ!
Radioline、簡単そうでしょ?
Radiolineでのシリアル通信の無線化
Radiolineでは、シリアル通信の代表格であるRS-232もしくはRS-485を、通信プロトコルに関係なく無線化することができます。
通常のRS-232では最大15m程度までしか通信距離を延ばすことができませんが、Radiolineを使えば電波の届く範囲まで通信距離を延ばすことができます。
またRS-485ではシールドツイストペアケーブルを何百mも敷設する必要がありますが、Radiolineでは無線で通信を行うので高価なケーブル敷設の必要がありません。
RS-232とRS-485は排他利用となり、同時に使用することができません。
Radiolineでシリアル通信を行う場合、同時にI/O通信をすることはできません。
シリアル通信に必要なもの
RadiolineでのI/O通信は無線モジュールの他に用途に応じたI/Oモジュールが必要ですが、シリアル通信の場合は、無線モジュールのみで通信することができます。
シリアル通信を行うのにいくつか設定が必要になります。その設定には、設定ツールと専用USBケーブルが必要です。


RS-232の場合
RS-232の場合は1:1のシリアル通信の無線化です。
RS-232を無線化する場合は、以下のように接続します。
図の11のコネクタに“5.1”“5.2”“5.3”の端子があります。
・5.1⇒RX(受信)
・5.2⇒TX(送信)
・5.3⇒GND
この3点を無線通信させたい機器と接続してください。
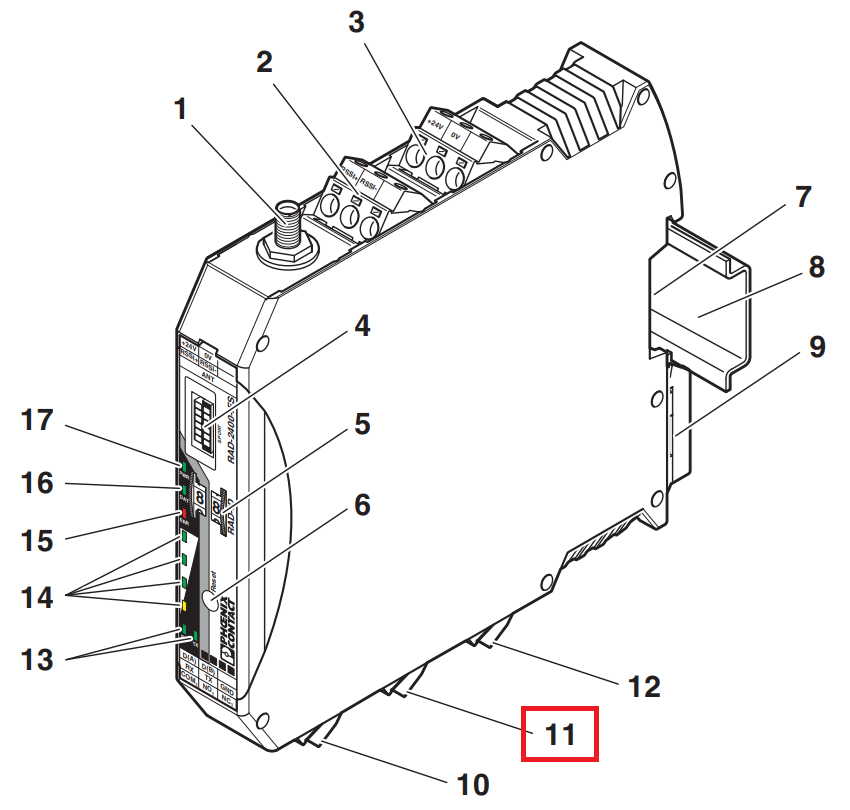
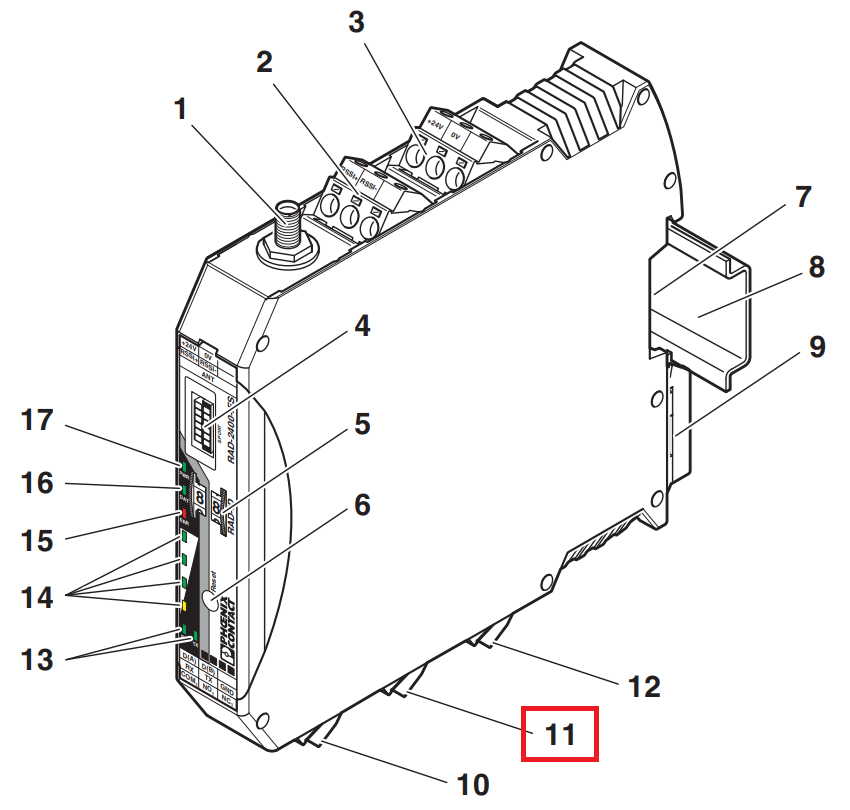
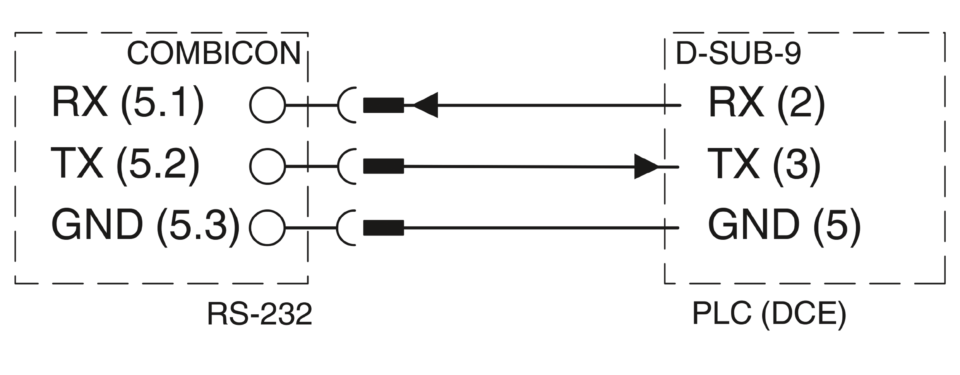
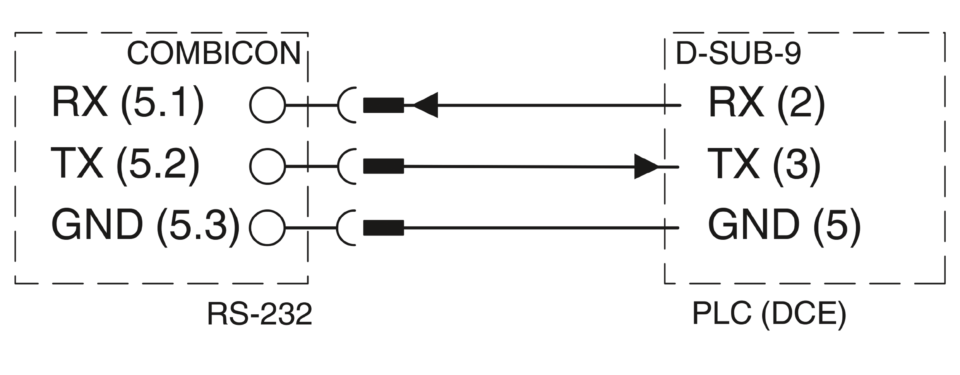
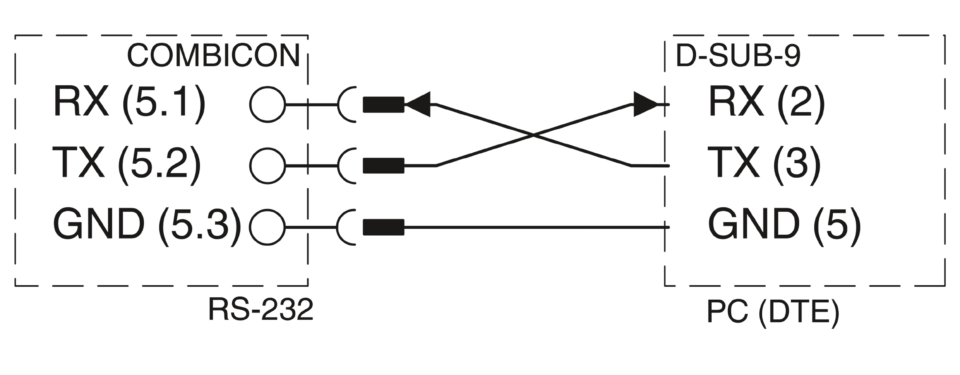
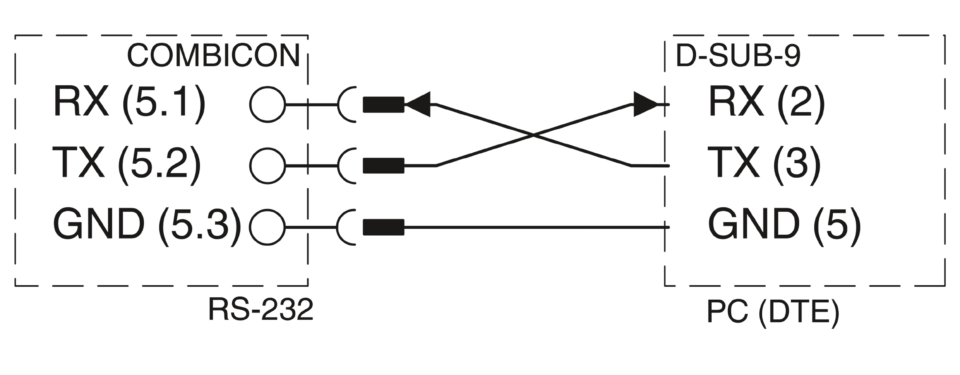
RS-485の場合
RS-485の場合は1:1のみならず、1:Nのシリアル通信の無線化も可能です。
1:Nの場合は次のようにシリアルデータがやり取りされます。
マスター側のRadiolineへシリアルデータが入力された場合は、接続されている全てのスレーブ側のRadiolineから同じシリアルデータが出力されます。(左図のイメージ)
一方で、あるスレーブ側のRadiolineへシリアルデータが入力された場合は、マスター側のRadiolineのみでしかシリアルデータは出力されません。(右図のイメージ)
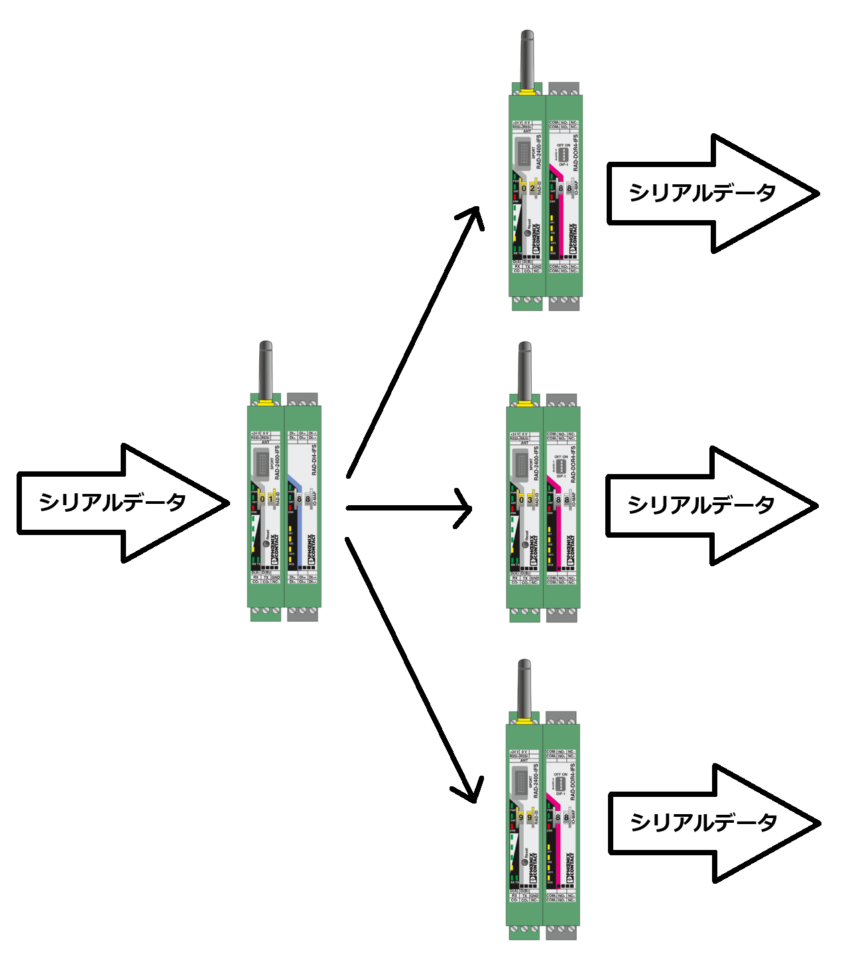
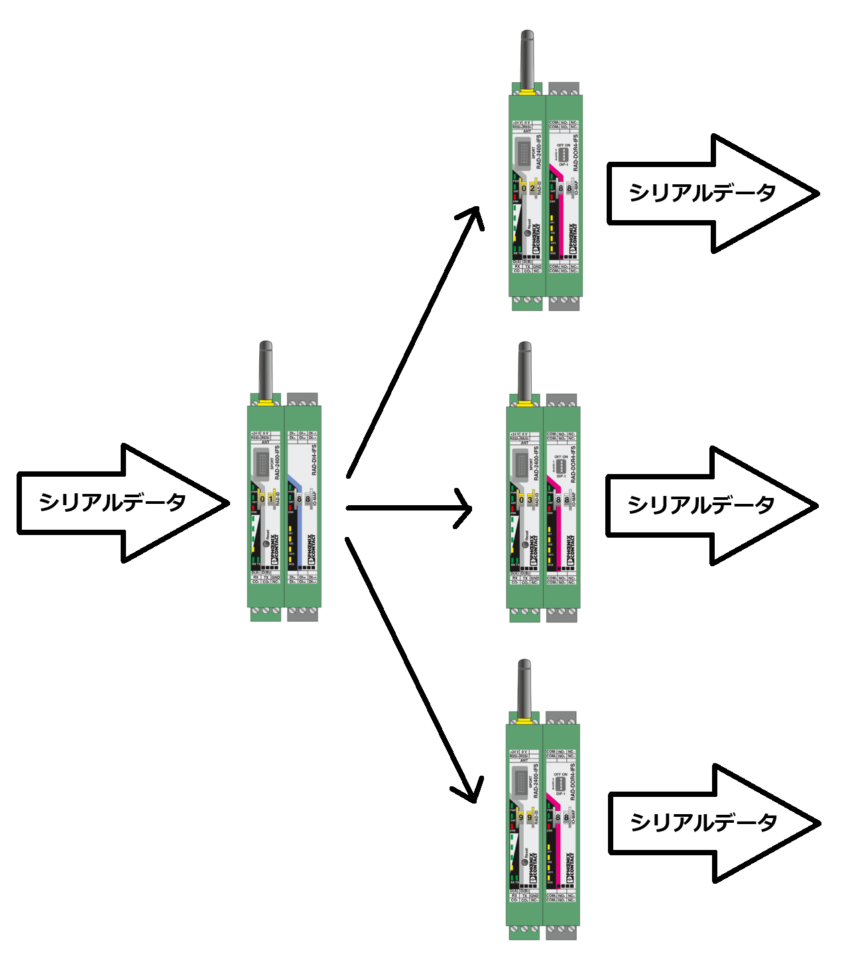
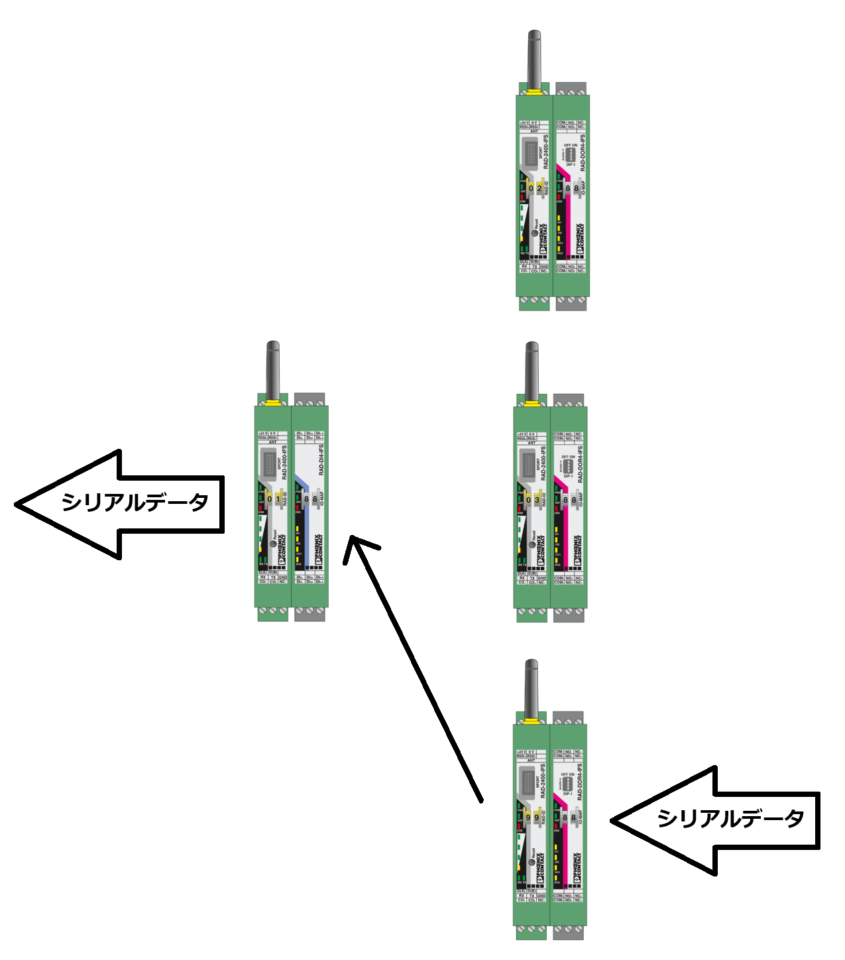
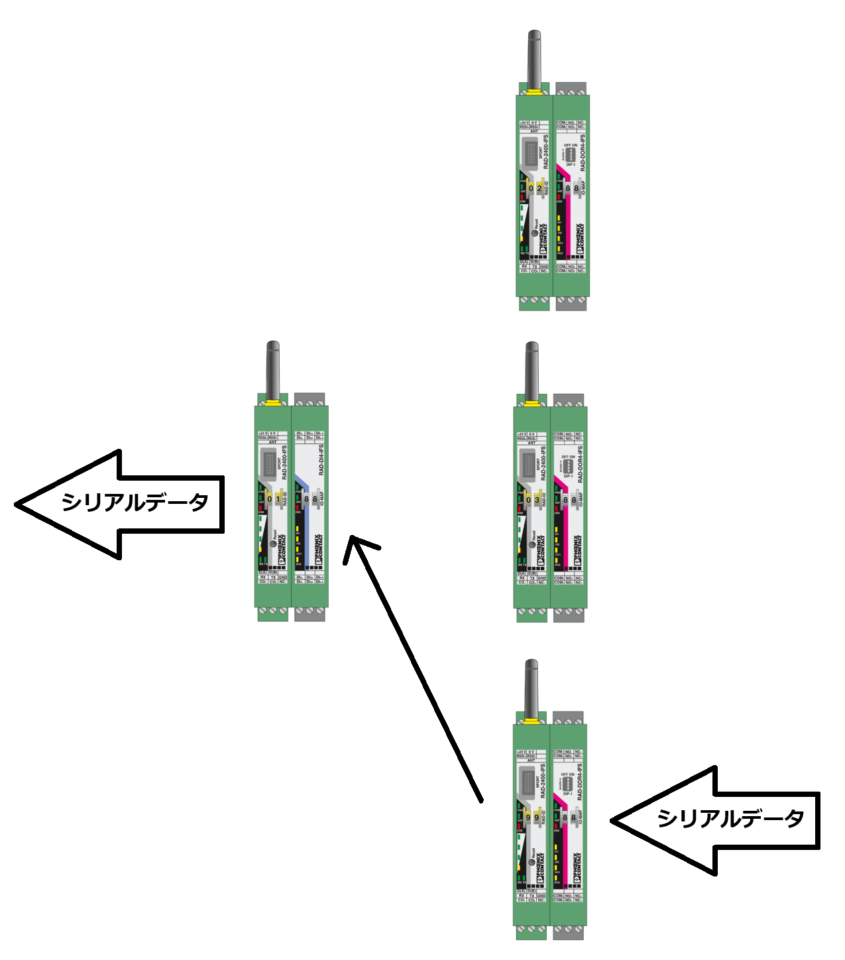
RS-485を無線化する場合は、以下のように接続します。
図の10のコネクタに“4.1”“4.2”の端子があります。
・4.1⇒D(A)(ー側)
・4.2⇒D(B)(+側)
この2点を無線通信させたい機器と接続してください。
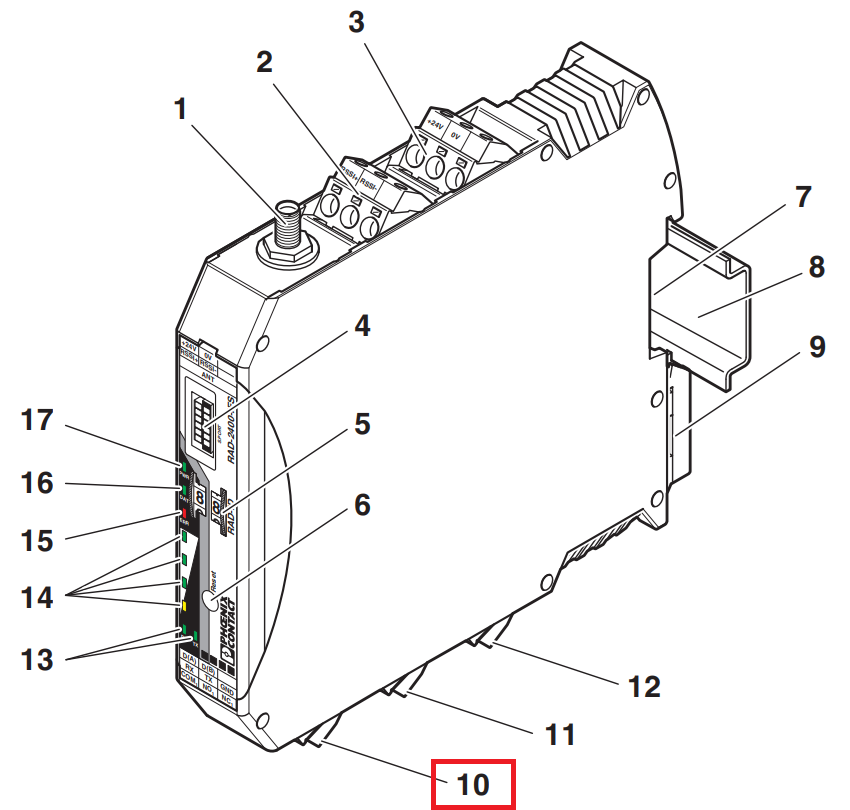
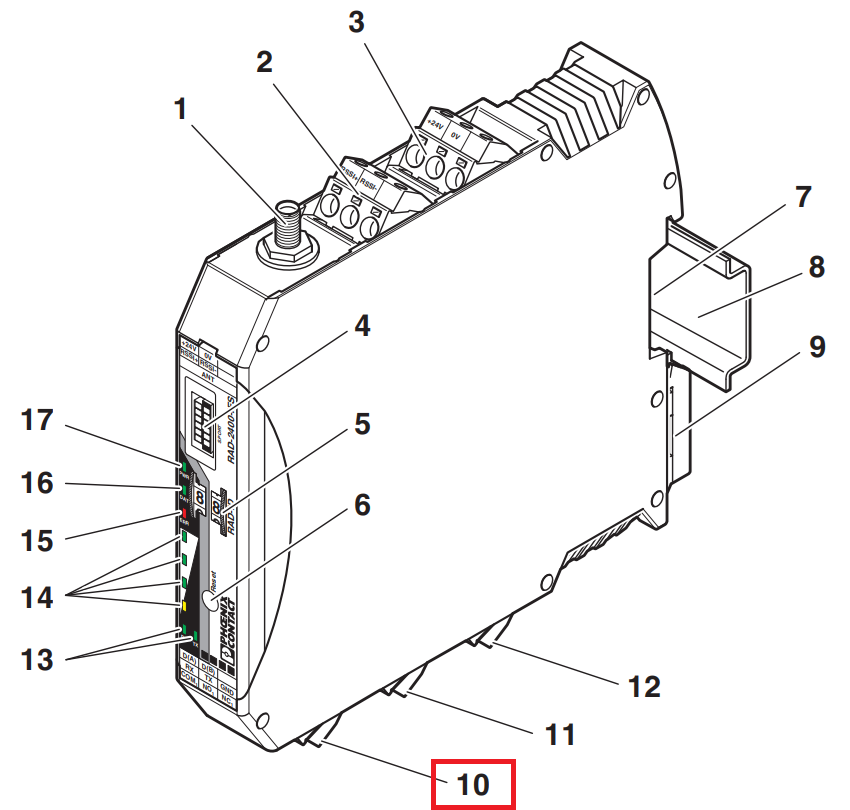


まとめ
今回はシリアル通信の無線化について御紹介しました。
設定ツール(PSI-CONF)については、別の機会に詳しく御紹介します。
今回は以上です。お読み頂きありがとうございました。
Radiolineをはじめとするワイヤレス機器の日本語カタログは、下のボタンからダウンロードできます。






